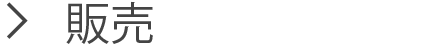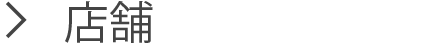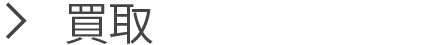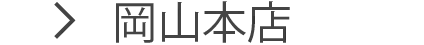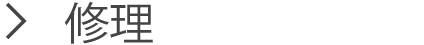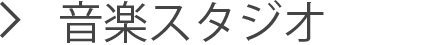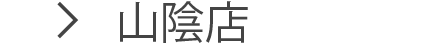「クラリネットを上達したいのだけど、どのようなエチュードを使えばいいのか分からない」「クラリネットの定番のエチュードを知りたい」このような悩みはありませんか?
実はエチュードは、自分に合ったレベルのものを使用しないと効率よく上達することはできません。
そこでこの記事では、吹奏楽CDのレコーディング30枚以上に携わった著者が、クラリネットのエチュードについて、難易度ごとに詳しく解説していきます。
この記事を読めばあなたに合ったエチュードが見つかり、上達すること間違い無しです。ぜひ最後までお読みください。
エチュードを練習に取り入れよう
主に吹奏楽部でクラリネットを演奏されている方は、以下のような練習を行っています。
- 基礎練習(ロングトーンやタンギングなど)
- 吹奏楽のために書かれた、基礎合奏用の教本
- 演奏会やコンクールに向けた曲の練習
エチュードとは「クラリネットの上達を目的とした曲集」です。
エチュードを行わず、曲や吹奏楽のための教本ばかり行っていては、上達のスピードはどうしても遅くなってしまいます。
なぜなら曲や吹奏楽のための教本は、クラリネットに特化して上達するように書かれているわけではないからです。
またロングトーンやタンギングなどの基礎練習は、クラリネットの上達には必要不可欠ですが、どうしても単調な練習になってしまいがちです。
エチュードは曲の形で書かれていることが多いので、より実践的な練習ができます。
音階・スケールのエチュード
まずはクラリネットのために書かれた音階のエチュードを紹介していきます。
クラリネットのために書かれた音階のエチュードは、吹奏楽のためにかかれた教本とは異なり、クラリネットの音域に合わせて書かれています。
初心者から上級者まで、音階練習は必須の練習となりますので、最低でも1冊はクラリネットのために書かれた音階のエチュードを所持して、練習に取り入れるべきです。
音階を練習するメリットは以下のものが挙げられます。
- 曲では普段なかなか使われない高音域や低音域の練習ができる
- 楽譜の譜読みが速くなる
- 奏法が安定する
音階練習は地味だし、短調で苦しい練習かもしれません。
しかし、上手いクラリネット奏者は必ず音階を重要視しています。騙されたと思ってでも良いので、スケールに取り組むようにしましょう。
それでは具体的なクラリネットのために書かれた音階のエチュードを見ていきましょう。
スケール・フォー・クラリネット(アイヒラー)
アイヒラーの「スケール・フォー・クラリネット」は、クラリネット奏者にとって最も有名なスケールのためのエチュードです。
全調のスケールをさまざまなバリエーションで練習することができ、演奏に必要な技術を習得できます。
初心者から上級者まで、幅広くおすすめできるエチュードで、音楽大学の入試でも使用されることがあります。
初心者が練習する際は、高い音はできる範囲で出せれば良く、場合によっては省略して練習するようにしましょう。
また難しい場合は、1番と2番だけでも練習して、様々な調に触れる練習方法がおすすめです。
アイヒラーが難しすぎる、という場合にはこちらのアルバートの「24の種々の音階と練習課題」というエチュードに取り組んでみると、ちょうどいいかもしれません。
特にバスクラリネット吹きは高い音を使うことがあまりないので、アルバートをメインにするのも良いでしょう。
逆にさらにレベルアップをしたいという上級者の方には、横川晴児先生が書かれた「音階と運指」に取り組んでみましょう。
最高音まで使ったスケールを練習することができます。
巻末に運指表もついており、替え指の勉強もすることができます。
クラリネット奏者におすすめのエチュードを難易度順に紹介
次にクラリネット奏者におすすめするエチュードを難易度順に紹介していきます。
どの順番でエチュードを取り組めばいいのか、参考になるはずです。
クラリネット学習のための合理的原則(グルーサン)
クラリネットを始めたての方から1年くらいの初心者の方に特におすすめのエチュードです。
ロングトーンや2つの音の移行から始まり、音作り・音色のための基礎練習が多く書かれています。
アンブシュアのトレーニングにも有効です。
ただしこのエチュードに運指表はないので、別途インターネットなどで運指は調べたうえで臨みましょう。
26のエチュード(ランスロ)
世界的なクラリネット奏者であるジャック・ランスロ氏が書いた初心者におすすめのエチュードです。
前述したグルーサンの「クラリネット学習のための合理的原則」が終わるか、同時並行で進めて欲しいエチュードです。
はじめは易しい曲から始まり、だんだんと曲の難易度が上がっていきますので、クラリネットを始めて数ヶ月から半年くらいの方であっても、始めることができます。
ロングトーンから、スラー、スタッカート、3連譜、後半はトリルやターンの練習など、 一曲ごとにテーマがあり楽しみながら上達をすることができるでしょう。
エチュードは一般的に楽譜だけ書かれており、学習するテーマを奏者自身が見つけなければならないのが主流ではありますが、このランスロのエチュードは全26曲、すべてに浜中浩一先生の解説付きなのが嬉しいポイント。
楽譜に書かれた音だけでなく、アーティキュレーションや強弱をつけること、その曲に適した吹き方を意識して練習できると、初心者向けのエチュードではありますが、かなり力がついてきます。
21のエチュード(ランスロ)
初心者にとって定番なのが前述したランスロの26のエチュード、そして上級者におすすめするのが、クラリネット界で最も有名なエチュードとも言える後述するローズの32のエチュードです。
この2つのエチュードの間には、かなりのレベル差があるので、ランスロの26のエチュードが終わった方が、ローズの32のエチュードに取り組むのは少し無理があります。
そこでおすすめするのがこのランスロの「21のエチュード」です。中級者向けのエチュードとなっています。
吹奏楽などでクラリネット歴が長いという方は、ランスロの26のエチュードは飛ばして、この21のエチュードから取り組んでみても良いかもしれません。
美しいゆったりとした曲と、速いパッセージの曲が交互に書かれている点が特徴となっています。
クラリネットのための32の練習曲(ローズ)
ゆっくりの曲と速い曲が交互にでてきて、番号が進むにつれ調号が増えていくため、様々な表現を学ぶことができるエチュードです。
難易度としては、中級者~上級者向けのエチュードとなっています。
前述したランスロのエチュードで習得したテクニックを、音楽的により発展させるための練習曲集です。
クラリネットのエチュードの中で最も有名ではありますが、音大入試の課題としても使われているため、初心者の方にとっては難易度が高すぎるかもしれません。
ゆっくりな曲は音楽表現の他に、複雑なリズムで書かれている曲も多くあるため、リズムが苦手な方にとってもおすすめできるエチュードと言えます。
エチュードでありながら、美しい旋律をもっているので、人気も完成度も非常に高い1冊です。
ローズは「26」から「32」「40」「20」の順で難易度が上がっていくエチュードを書いています。
クラリネット奏者の座右の銘(ジャンジャン)
このエチュードはこれまで紹介してきたエチュードとは毛色が違い、曲として書かれていると言うより、6つの技術練習に特化して技術の習得を目指すエチュードとなっています。
6つの技術とは具体的には次の通りです。
- トリル
- 左手のための特別練習
- 右手のための特別練習
- スタッカート
- スケール・アルペジオ
- 音色
音楽大学でも時々用いられているエチュードと言うことで難易度も高いです。
エチュードで身につけた技術をよりグレードの高い楽器で披露してみませんか?

エチュードで技術を磨くことは非常に重要ですが、やはりグレードの高い楽器で演奏した方が良い音が奏でられるもの。
楽器のグレードを上げて、より充実した音楽ライフを送ってみませんか?
新品の楽器は手が出ない、という方であっても、「服部管楽器」であれば中古楽器も多数取り揃えています!
クラリネットを専門にしているスタッフが、あなたの楽器選びを1から丁寧にサポートします。
下のボタンから、ぜひお気軽にお問合せくださいね♪