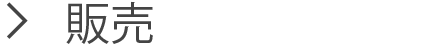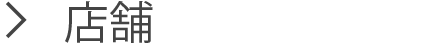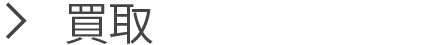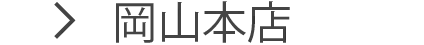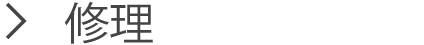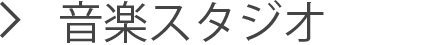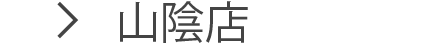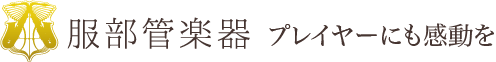「クラリネットの高音が出ない」「きれいに高音域を出したい」このような悩みはありませんか?
実は高音域の吹き方には明確なコツがあり、それを理解していないと練習をしていてもなかなか高音域を扱うことはできるようになりません。
そこでこの記事では、吹奏楽CDのレコーディング30枚以上に携わった著者が、クラリネットの高音域を出すコツ、きれいな高音域の吹き方などを詳しく解説していきます。
この記事を読むことで、クラリネットの高音域の奏法を理解することができ、上達が早くなりますので、ぜひ最後までお読みください。
クラリネットで高音域を出すときの息の使い方
まずクラリネットの高音を出すためには、息のスピードを上げることが大切です。
音の出だしからスピードのある息を出せていないと高音域は当てることができません。
スピードのある息を出すには、口の中を狭い状態に保ち、唇の筋肉を真ん中に集めて息の出口を狭くすることが必要になります。
ホースの先をつまむと、水の勢いが増すのと同じ要領で、細い息を出すと息のスピードが増し、息圧が上がります。
実際に息を出してみると分かりますが、細く・速い息を出そうとすると口の中は狭い状態で、かつ唇の筋肉が真ん中に集まっていることが必要です。
ストローのような細いものに息を入れるつもりで、勢いよく楽器に息を吹き込みましょう。
また高音域を当てるには、息が上向きで演奏される必要があります。
ベルの方向に息を向けてしまうのは、下向きの息です。
ベル方向ではなく、マウスピースの上側に息を当てるようにしましょう。
真っ直ぐ正面に息を出すようにすると上向きの息となります。
楽器を手前に引き寄せるつもりで吹くと、上向きの息が入りやすくなるかもしれません。
クラリネットを構える角度は、体格などによって異なるので、色々研究してみてください。
息の向きを変える練習としては、下のドの運指のまま、レジスターキーを押したソの音、その上のミの音、その上のラの音、と順番に息の向きだけ変えて出すように練習します。
この練習で音域ごとに息の向きを自由にコントロールできるようになれば、息を上向きに入れる感覚が理解できるでしょう。
クラリネットで高音域を出すためのアンブシュア
アンブシュアの基本の形は音域によっては変わりません。しかし、締め具合は音域によって変わってきます。
クラリネットで高音域を出すときは、低い音を出すときに比べて、少し強くリードに圧力をかけます。
ただし、リードに圧力をかけ過ぎてしまうと、つまった音や音がつぶれてしまう原因にもなるので注意しましょう。
リードに圧力がかかっても、良い音がしていればOKです。
リードに圧力をかけるには、「下顎で噛む」「口の周りの筋肉を集める」という2つのアプローチで行います。
ある程度「噛む」ことはしていますが、メインは「口の周りの筋肉を集める」ということを意識してください。
口の周りの筋肉は普段使わないので、楽器を吹かないとつかない筋肉です。
一方で、普段から物を食べているので、噛む筋肉は十分発達しています。
そのため、油断すると噛む力に頼りすぎてしまうことがあるので、注意してください。
ただしクラリネットを始めて数年、という方はまだ口の周りの筋肉がしっかり発達していないかもしれません。
その場合は、少し強めに噛んでしまってもとりあえずは問題ありません。
まずは高音域をしっかり当てて、感覚をつかむことが大切です。
なお、高音域に限らず、基本のアンブシュアの作り方はこちらの記事で解説していますので、ぜひ読んでみてください。
>【初心者向け】クラリネットのアンブシュアの作り方とコツを徹底解説!&よくある悩みに回答
高音域が上手く出ないときのその他のチェックポイント
ここまで解説してきた高音域の奏法を試しても、まだ高音域が上手く鳴らないという方に向けて、試してほしい・意識してほしいポイントを解説していきます。
喉に力は入ってませんか?
喉に力が入ってしまうと、息の流れが悪くなってしまいます。
息の流れが悪いと、高音域を含め、良い音が出ません。
また喉に力が入った状態だと、舌が下がってしまい、口の中が広くなってしまっている可能性もあります。
口の中が広がってしまうと、前述した通り、高音域を出すために必要な細く・速い息を出すことができなくなってしまいます。
右手親指できちんと楽器を支えられていますか?
クラリネットの正しい吹き方は、右手親指で楽器を少し押し上げている状態です。
この押し上げる力でクラリネットを支えています。左手を使わなくても、楽器を支えられる状態であることが大切です。
この支えがないと、口だけで楽器を支えることになり、かなり無理のある奏法になってしまいます。
楽器やリードは正しい状態ですか?
前提として、楽器の調整が狂っている、マウスピースを選定できていない、正しくリードが育てられていないような状況では、プロであっても高音域を演奏することは困難です。
改めて自分の楽器やアクセサリーが、高音域を出せるような正常な状態であるかはチェックするようにしましょう。
正しいリードの育て方はこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。
>【クラリネット】リードの育て方・選び方~正しく理解して音色もコストパフォーマンスも向上
日々の練習で気をつけたいこと
日々の基礎練習(ロングトーン・タンギング・音階練習など)から高音域を演奏することが、苦手意識をなくすには必要なこととなります。
高音域は吹き慣れて、感覚をつかむことが非常に重要です。
練習時にいきなり高音域を出すのは難しいため、出しやすい音から順次上がっていくと良いでしょう。
順次上がっていくことで音のイメージもしやすくなります。
クラリネットの高音域をきれいに、柔らかい音で出す方法(中・上級者向け)
クラリネットの高音域自体は出すことができる、ただきれいな音で出すことができない人向けの解説です。
クラリネットの高音をきれいに出すためのポイントは「脱力」です。
初心者のうちは、高い音はある程度噛むようにしないと、高音域を出すことができません。
そのため高音域は、力を入れて吹く癖が残ってしまっています。
高音域がつぶれてしまったり、硬い音になってしまう原因の多くは「噛み過ぎ」です。
では噛まずに音を出すにはどうすればよいか、それは息のコントロールをより洗練させます。
中低音の音を吹くときと同じアンブシュアにしておきつつ、息だけで高音が出る吹き方を探します。
オクターブ下の音を吹いて、アンブシュアを変えずにオクターブ上の音を出す、その際にきちんとオクターブ上の音が出る吹き方を探すように練習するのが効果的です。
また、ダブルリップで練習することも効果的です。
ダブルリップとは、下唇を巻くのと同じように、上唇も巻いて、オーボエのように演奏する奏法のこと。
演奏で使うことはまれですが、練習方法としては有効な奏法です。
ダブルリップで練習してみると分かりますが、噛むことができません。
つい噛んでしまう癖が抜けない人は、ダブルリップを使って強制的に噛めない状態を作って、息だけで高音をコントロールする練習もおすすめです。
クラリネットの高音域をきれいに出すことは、決して簡単なことではないので、根気強く練習してみてください。
高音域を出しやすい、グレードの高い楽器に買い替えてみませんか?

ここまで解説してきた奏法でも高音域を出すことはできますが、やはりグレードの高い楽器で演奏した方がさらに高音域が出しやすいもの。
楽器のグレードを上げて、より充実した音楽ライフを送ってみませんか?
新品の楽器は手が出ない、という方であっても、「服部管楽器」であれば中古楽器も多数取り揃えています!
クラリネットを専門にしているスタッフが、あなたの楽器選びを1から丁寧にサポートします。
下のボタンから、ぜひお気軽にお問合せくださいね♪