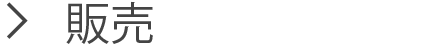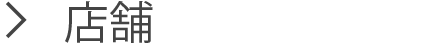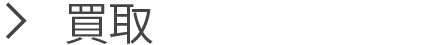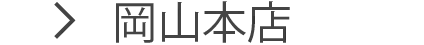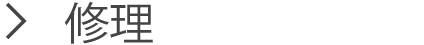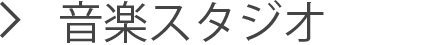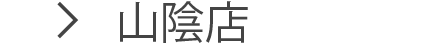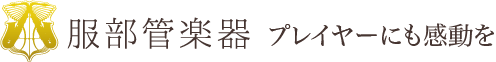「クラリネットを上達するためにはどんな練習をすればいいのか知りたい」「時間がない中でどんな練習メニューを優先すればいいかわからない」このような悩みはありませんか?
実はクラリネットで行うべき基礎練習はある程度テンプレート化されて決まっており、効果の高い練習は間違いなくあります。
そこでこの記事では、吹奏楽CDのレコーディング30枚以上に携わった著者が、クラリネットを吹くうえで誰もが行うべきである基礎練習メニューを紹介していきます。
この記事を読めば、クラリネットに必要な練習メニューを知ることができ、あなたの上達にきっと役立てることができます。
ぜひ最後までお読みください。
クラリネット奏者が絶対に行うべき基礎練習とは
クラリネットを上達するためには、曲練習ばかりしていてはいけません。
基礎練習が必ず必要になってきます。
曲練習ではその曲に関するテクニックしか身につけることはできませんが、基礎練習であればどんな曲でも使える、網羅的な技術を習得することができるからです。
ここで紹介する基礎練習を参考に、練習メニューを考えてみてください。
ロングトーン
ロングトーンは全ての基礎となる練習で、管楽器奏者であれば時間がなくとも必ず行いたい練習の1つです。
ロングトーンがもたらす効果は、まっすぐブレない息を作ることができるという点です。
これは当然と思われるかもしれませんが、このまっすぐブレない息というのは、全ての技術の土台となります。
ゆっくりな曲を歌うときも、速い連符を吹くときも、このまっすぐブレない息を使って演奏するからです。
音をまっすぐ伸ばすためには、音を伸ばしている間、息もアンブシュアなどの奏法も、一定に保ち続ける必要があります。
逆に言えば、ロングトーンで音が震える・ロングトーンが続かない理由は、息や奏法が一定に保てていないということです。
また音を伸ばすというシンプルな練習だからこそ、息以外にも自分の演奏を見直すことができます。
アンブシュアや姿勢、フォームなどを見直してみましょう。
エチュードや曲の練習では、指やリズムなど気にすべき点が多岐にわたるため、奏法に集中しきることは難しいです。
一方でロングトーンであれば、決まった音を伸ばすだけなので、自分の奏法に集中できます。
ロングトーンをしながら、まず見直したいのは「アンブシュア」です。
クラリネットのアンブシュアについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。
>【初心者向け】クラリネットのアンブシュアの作り方とコツを徹底解説!&よくある悩みに回答
クラリネットの場合、レジスターキーを使ったロングトーンだけでも行っておくと効果は高いです。
レジスターキーのロングトーンは次の通りに行います。
①メトロノームのテンポを♩=60にセットする
②最低音の「ミ」の音を4拍伸ばす
③ブレスをしないでレジスターキーを押して「シ」の音を4拍伸ばす
④合計8拍伸ばしたらブレスを取り、「ファ」→「ファ#」と半音ずつ上がって②~③を同様に繰り返す
⑤この練習を左親指「ファ」まで繰り返す
このレジスターキーを使ったロングトーンを行うことで、低音から高音までまんべんなく練習できるほか、アンブシュアの柔軟性も磨くことができます。
音階・スケール
音階・スケール練習は、練習時間が少なくても、著者は必ず取り入れています。
ほとんどの曲が音階をもとに構成されており、演奏の基礎となるからです。
音階練習に取り組むメリットはいくつもあります。
- 譜読みが速くなる
- 音楽の調性や緊張・解放を理解でき、楽譜を正確に演奏できる
- 「広い音域で、同じ息の使い方・同じ奏法で演奏する」練習ができ、演奏が安定する
クラリネットでおすすめのスケール教本はこちらのアイヒラーの教本です。
練習時の注意点としては、必ずメトロノームを使って練習するようにしてください。
タンギング練習
音の立ち上がりは、音楽の第1印象を決める非常に重要な要素です。
美しいタンギングを習得するまでには時間がかかるので、日々の練習から少しずつでも取り組んでおきたいもの。
クラリネットの美しいタンギング方法や、練習の取り組み方などはこちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ読んでみてください。
>【クラリネット】タンギング完全解説!~基礎から応用、ダブルタンギングまで
高音域の練習
クラリネットは高音域の運指や演奏方法が、他の音域と比較して難易度が高いため、習得までに時間がかかります。
そのため高音域だけを取り出して練習時間を確保するのも有効な方法です。
ただし、長く高音域ばかりを練習すると、口が疲れてしまいやすいので、口が痛くならない程度の練習時間にとどめておくようにしましょう。
高音域の奏法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
>【クラリネットの高音域】きれいに・柔らかい音で出すためのコツを徹底解説
練習とあわせて行いたい、リードの管理について
練習メニュー、というと少し外れてしまうかもしれませんが、時間をかけて行いたいのは「リードの管理」です。
(リードの管理にも技術の習得が必要となるため、練習と言えなくもありませんが…)
新品のリードをそのままで使うことはおすすめしません。
新品のままリードを使ってしまうと、状態変化が急に起こってしまったり、寿命を早くむかえてしまう恐れがあるからです。
そのためリードを「育てる」という過程が必ず必要になります。
リードを育てるには、毎日クラリネットを吹く方であっても1週間から10日程度はかかってしまうため、練習や合奏、本番で使えるリードの他に、育てているリードを持つのが一般的です。
このリードの育て方については、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ読んでみてください。
>【クラリネット】リードの育て方・選び方~正しく理解して音色もコストパフォーマンスも向上
楽器を使えないときの練習方法について
よく質問を受けるのが、「楽器を吹けないときの練習方法は何かないのか?」といったものです。
その質問を受けた際に著者は迷わず、「良い音楽を聴くこと」と回答しています。
良い音楽を聴くことは、作業中や移動中であっても行うことができます。
著者自身も時間を見つけては、良い音楽を流すことを長らくしてきました。
良い音楽を聴くことが重要なのは、どのように曲を演奏したいのか、イメージを作る練習になるからです。
どんなに技術を磨いても、イメージできていない音は出すことができません。
さらに良い音楽にするためにイメージを磨く、イメージした音を出すために技術を磨く。イメージと技術は楽器上達にとって、車の両輪のようなもの。
車は片輪では走行できないように、良い音楽を聴くことは、楽器を使った練習と同じくらい重要です。
今より良い演奏をするために、楽器の買い替えも検討してみませんか?

練習も大切ではありますが、演奏を変えるにはやはり楽器の力は不可欠です。
今の楽器を下取りに出して、楽器のグレードを上げて、より充実した音楽ライフを送ってみませんか?
新品の楽器は手が出ない、という方であっても、「服部管楽器」であれば中古楽器も多数取り揃えています!
クラリネットを専門にしているスタッフが、あなたの楽器選びを1から丁寧にサポートします。
下のボタンから、ぜひお気軽にお問合せくださいね♪