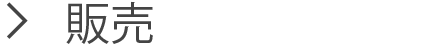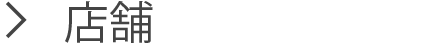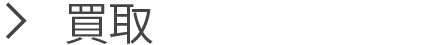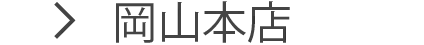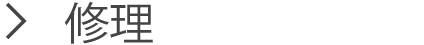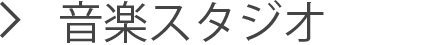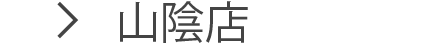「どのように吹いてもリードミスが無くならない」「大事なコンクール・コンサートなので、絶対にリードミスをしたくない」このような悩みはありませんか?
実はリードミスを完全になくすことは至難の業、というよりも不可能に近いです。プロの演奏家であっても、頻度は低いですがリードミスをしてしまうことがあります。
そこでこの記事では、吹奏楽CDのレコーディング30枚以上に携わった著者が、クラリネットのリードミスについて、その発生原因と対策を詳しく解説していきます。
この記事を読んで実践していけば、あなたのリードミスは劇的に減るはずです。ぜひ最後までお読みください。
リードミスが発生する原因とその対処法
リードミスとは演奏中に「ピー」や「キー」といった、意図していない高音が出てしまう、音がひっくり返ってしまう演奏上のミスのことを言います。
このリードミスが発生する仕組みは、狙った音ではない意図しない高い倍音が出てしまうというものです。
私たちがクラリネットで演奏している音には実際に鳴らしている「基音」と呼ばれる音の他に、基音より高い音である「倍音」という音が含まれています。
倍音は普段はあまり聴こえることはないのですが、リードミスが発生するような環境下では、この倍音が前面に出て聴こえてしまうことがあります。
ではどのような環境下でリードミスは発生しやすいのか、リードミスの原因とその対処法を見ていきましょう。
リードミスの原因① 楽器に問題がある
リードミスは奏法の原因以外にも、楽器のコンディションによっても引き起こされることがあります。
リードミスの原因の1つとなるのがタンポ(特に上管部分)のコンディション悪化です。
タンポは消耗品なので、正しく取り扱っていても必ず劣化してしまいます。
定期的にリペアに持っていき、楽器の調整を行うようにしましょう。
タンポの劣化を確認する方法は次の通りです。
①上管・下管を分解する。
②指を全部押さえ、下の部分を手のひらでふさぐ
③上から息を吹き込む
②・③は上管・下管それぞれで行います。
この際、正常なのは息が入らない状態です。タンポ部分から息が漏れてしまう場合、タンポの劣化が疑われます。
簡単にできますので、試してみてください。
リードミスの原因② 指がふさがっていない
リードミスの原因で最も多いと言えるのが、指がきちんとふさがっていないケースです。
リードミスというと、「リード」という言葉から、口元やアンブシュアが原因でないかと疑いたくなりますが、実は指に原因があることが多いと言えます。
特に中学生など、指が細い方は、より丁寧にトーンホールをふさぐように注意してみてください。
特に左右の薬指がトーンホールよりも上に来すぎてしまうことが多いです。
また意図せずソ#のキーや右手のサイドキーに触れて、トーンホールが開いてしまうケースもあります。
指先ではなく、面積の広い指の腹でトーンホールをおさえるようにすると上手くいきやすいです。
リードミスの原因③ アンブシュア
深くマウスピースをくわえるほど、倍音が出やすくなることから、リードミスが発生する原因になります。
長時間吹いているとリードミスが多くなる方は、アンブシュアに問題があるかもしれません。
アンブシュアを維持する体力・筋力が足りていない状態だと、吹いていくと徐々に口を大きく開くようになっていってしまいます。
口が大きく開くようになってしまうと、マウスピースを深くくわえてしまうので、リードミスが起こりやすくなります。
また、噛み過ぎている、または緩すぎるアンブシュアでもリードミスが発生しやすいです。
噛みすぎてしまうアンブシュアは、力んで演奏しがちな初心者に多く見られます。また大きな本番などで緊張してしまうと噛んでしまいがちです。
噛み過ぎてしまうと、リードの振動を妨げてしまいます。それに対して強い息を吹き込むと、リードが上手く振動できず、リードミスとなってしまうのです。
緩すぎるアンブシュアは、クラリネットを吹き始めるとき、アンブシュアの準備がきちんとできていないのに吹き始めてしまうと起こりがちです。
リードに適切な圧がかかっていないと、本来振動させない下の方の部分まで振動しようとします。
するとリードの厚い部分と薄い部分がバランスよく振動しないため、リードミスとなります。
アンブシュアのキープ、特に上の歯と下の歯の隙間のキープを意識するようにしましょう。
その他にもクラリネットを演奏する際に身体を動かした反動で、アンブシュアが崩れてしまうとリードミスになりやすいので注意してください。
なお、クラリネットの正しいアンブシュアの作り方はこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。
>【初心者向け】クラリネットのアンブシュアの作り方とコツを徹底解説!&よくある悩みに回答
リードミスの原因④ リードミスしやすいリードを使ってしまっている
リードの個体差によって、リードミスしやすいリードとリードミスしにくいリードに分かれます。
明らかに吹きにくいリードだけや欠けてるリードは論外ですが、一見、音が出しやすかったり、音色が良いリードであっても、リードミスしやすい個体は確かに存在するので、厄介な問題です。
リードによってリードミスの回数が大きく違う場合は、奏法ではなく、リードが原因であると疑ってみましょう。
また硬すぎたり、柔らかすぎたりするリードもリードミスが発生しやすいです。
なお、どのリードを使っても、あまりにリードミスが多い場合はマウスピースを疑ってみましょう。
リードミスの原因⑤ リードのセッティングの仕方が良くない
初心者に多いミスとして、リードのセッティングの仕方が良くないケースがあります。
リードが左右どちらかに傾いてセットされていたり、リードをつける位置が上すぎたり下すぎたりする場合です。
なお、リガチャーも正しく装着するように気をつけてください。
順締めと逆締めのリガチャーの違いもありますので、注意して取り扱うようにします。
リードをセッティングする位置は、リードとマウスピースの相性や音色の好みでも変わってきますが、基本のセッティング方法をおろそかにしないようにしましょう。
リードミスの原因⑥ タンギングの方法が間違えている
タンギングの際、舌とリードが触れる面積が大きくなってしまっている場合、リードミスが起こりやすくなります。
舌の1点とリードの1点、点と点でタンギングを行うのが、正しいクラリネットのタンギングです。
正しいタンギングのやり方はこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。
>【クラリネット】タンギング完全解説!~基礎から応用、ダブルタンギングまで
リードミスの原因⑦ 息の使い方を誤っている
鳴らす音に対して、正しい息の方向で吹けていればリードミスは発生しません。
逆に言えば、間違えた息の方向で演奏してしまうとリードミスになります。
息の方向が上に行くほど、倍音が鳴りやすく、リードミスとなりやすいので、下に息を吹き込むよう意識をしましょう。
また息のスピードにも注意を払う必要があります。
息のスピードを上げすぎると、倍音が鳴りやすく、リードミスになりやすいです。
では息をゆっくり入れれば良いのかというと、それでは単純に良い音が鳴りません。
正しい息の方向・息の量・息のスピードで演奏すればリードミスは起こりません。
これを身につけるには、レジスターキーを使ったロングトーンが効果的です。
楽器のグレードを上げて、リードミスを防いでみませんか?

やはりグレードの高い楽器で演奏した方が演奏しやすく、リードミスは発生しにくいもの。
楽器のグレードを上げて、より充実した音楽ライフを送ってみませんか?
新品の楽器は手が出ない、という方であっても、「服部管楽器」であれば中古楽器も多数取り揃えています!
クラリネットを専門にしているスタッフが、あなたの楽器選びを1から丁寧にサポートします。
下のボタンから、ぜひお気軽にお問合せくださいね♪