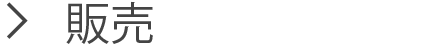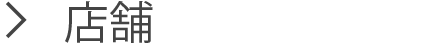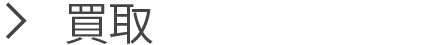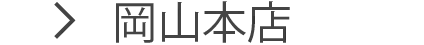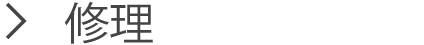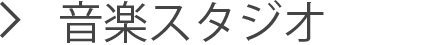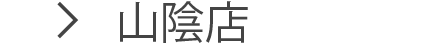「クラリネットのタンギングの仕方がわからない」「もっと綺麗なタンギングを習得したい」このような悩みはありませんか?
実はタンギングが上手くなるためのコツは明確に存在します。
そこでこの記事では、吹奏楽CDのレコーディング30枚以上に携わった著者が、クラリネットのタンギングについて、詳しく解説していきます。
クラリネットのタンギングの基礎から応用まで深掘りして解説していますので、どなたにとっても上達に役立ちます。ぜひ最後までお読みください。
クラリネットのタンギングとは?
クラリネットは息を入れることでリードが振動します。
このリードの振動こそがクラリネットの音です。
リードの振動を舌で止めることで、息を入れたままでも音が切れた状態を作る、これがタンギングとなります。
つまり音を切るために、お腹で息の流れを止める必要はなく、ロングトーンのように息を出したままでも、タンギングによって音を切ることができます。
クラリネットのタンギングの仕方・やり方
クラリネットのタンギングでは、吹きながら「トゥ(Tu)」や「ドゥ(Du)」と発音すると、音が切れるようになります。
舌の先端から数ミリ奥に行った部分と、リードの先端、もしくは先端からやや奥を狙うようにします。
人によって骨格や舌の長さは違うので、つきやすい位置を研究してみてください。
前述した通り、息はロングトーンのように出しっぱなしで、舌だけ動かします。
舌がリードに触れることで、リードの振動が止まり、音も止まります。
音と同時に息まで止めてしまうと、次の音の立ち上がりが遅くなってしまいます。
汚いタンギングからの脱却!タンギングのコツについて
「綺麗にタンギングができない」「速いタンギングができない」と悩む人は多いです。
ここではそれらの悩みを解決する、タンギングのコツを解説していきます。
コツ① 舌とリードは「点」と「点」でつく
舌は筋肉で、クラリネットのリードの振動を止めるには十分すぎるくらいの力が備わっています。
リードを叩くつもりでタンギングしてしまうと力が入りすぎです。舌の力は抜き、弱く触れるくらいの意識でタンギングするようにしてください。
また広い面積で舌とリードが触れてしまうと、かえって雑音が入ってしまいます。
そこで舌の1点とリードの1点、点と点でタンギングを行うようにします。
つまり舌とリードが触れる面積は、限りなく小さくなるのが正しいタンギングです。
コツ② 舌はリードから近いところに置いておく
舌がリードに触れれば音は止まり、舌とリードが離れれば音が鳴ります。
言い換えれば、リードから1mmでも舌が離れていれば、音が鳴るということができます。
舌はなるべくリードから離さないようにセットしてください。
そうすることで、舌が動く距離が短くなり、結果的に速いタンギングを行いやすくなります。
口の中の容積を狭いアンブシュアにしておくと、舌とリードの距離を近くにしておきやすいです。
コツ③ 動かすのは舌だけ(アンブシュアは変わらない)
タンギングをして舌を動かそうとするとき、下顎(あご)まで動いてしまう人がいますが、これは避けましょう。
下顎まで動かしてしまうと、速いタンギングを行うことができません。(下顎は速く動かせないから。)
また下顎が動くことで、音程もぶれてしまう可能性があります。
アンブシュアを作って、「トゥ(Tu)」や「ドゥ(Du)」と発音しにくい方はアンブシュアの作り方を間違えている可能性があります。
クラリネットのアンブシュアについてはこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひお読みください。
>【初心者向け】クラリネットのアンブシュアの作り方とコツを徹底解説!&よくある悩みに回答
コツ④ 舌を素早く引く
舌がリードに触れたら、素早く舌を離すように意識しましょう。
テンポがゆっくりのタンギングであっても例外ではありません。
素早く離すことでタンギング時の雑音を防ぐことができます。
特に雑音の入りやすい高音域のタンギングでは効果的です。
素早く引くことを意識しすぎて、舌がリードから離れすぎたり、下顎が動いてしまうのが良くない、というのは前述した通りです。
コツ⑤ 息のスピードをキープする
タンギングであっても、普段のロングトーンで吹くときと同じように、速い息で練習するようにしましょう。
タンギングを行うと、息は入れにくくなります。
これは息を流したいのに、タンギングの都度、流れがせき止められてしまうからです。
普段通りの息を入れても上手くいかない場合、息のスピードが足りていない可能性がありますので、息のスピードを上げて試してみてください。
タンギング練習では舌ばかりに意識がいってしまい、息がおろそかになりがちです。
管楽器演奏は何よりも息が重要ですので、息に関してもしっかり意識して、タンギング練習に臨んでください。
タンギングの練習方法
次に具体的なタンギング練習について解説していきます。
練習方法① 徐々に速くして練習する
次の譜例を使い、メトロノームをかけて練習します。テンポは♩=60~120程度にセットし、できるテンポから行ってみてください。

初心者の方は、音域は最低音の「ミ」から高い「ド」まで練習すると良いと思います。(中上級者はさらに高い音で練習してみみましょう。)
まずは16分音符が入るゆっくりなテンポから正しい奏法を身につけ、徐々に速いテンポで練習していってください。
練習方法② スケール(音階)を使う
練習方法①でタンギングの基本的な奏法が身に付いたら、次はスケール(音階)を使って練習するのがおすすめです。
まずは音階をスラー(タンギングなし)で演奏し、息づかいやアンブシュアの状態など、どのように自分が演奏しているのかを観察します。
スラーで良い音がでるようになったら、いよいよタンギングを加えてみます。
その際に、スラーで吹いた良い状態から「舌だけを足す」つもりで演奏するようにします。
舌だけ独立していることが重要です。
舌を動かすことで、息づかいやアンブシュアなどの奏法が崩れないように注意しましょう。
練習方法③ エチュードを使う
タンギングを曲の中で実践するために、エチュードを使った練習も効果的です。
エチュードでは通常のタンギングの他、「スタッカート」も登場してきます。
クラリネットのスタッカートは、舌とリードのつく時間が長いだけです。
舌とリードのつく時間が長いと、音の出ていない時間が長くなり、音自体が短くなります。
その際、通常のタンギングと同じように、息は入れっぱなしにする(スタッカートの都度入れない)ことと、息づかいやアンブシュアなどの奏法が変わらないことが重要になってきます。
初心者におすすめのエチュードは「ランスロ:26のエチュード」です。いくつかスタッカート系の曲があります。
中級者におすすめのエチュードは「ランスロ:15のエチュード」です。
上級者におすすめのエチュードは「ローズ:32のエチュード」の偶数番号です。
クラリネットのダブルタンギング
ダブルタンギングを習得すれば、通常のタンギング(シングルタンギング)よりも速くタンギングを行うことが可能になります。
シングルタンギングでは「トゥ(Tu)」や「ドゥ(Du)」と発音していたのに対して、ダブルタンギングでは「トゥクトゥク(TuKuTuKu)」や「ドゥグドゥグ(DuGuDuGu)」と発音します。
違いは舌のつく位置です。「トゥ(Tu)」や「ドゥ(Du)」は舌先からわずかに奥でリードに触れるのに対し、「ク(Ku)」や「グ(Gu)」はそこよりさらに奥でリードに触れます。
まずは「ク(Ku)」や「グ(Gu)」のタンギングだけで練習するようにしてみましょう。
これができたら次に「トゥクトゥク(TuKuTuKu)」や「ドゥグドゥグ(DuGuDuGu)」をゆっくりから練習します。
「トゥ(Tu)」と「ク(Ku)」の発音に差がでないように、ゆっくりのテンポでも舌は速く動かすように意識しましょう。
慣れてきたら徐々にテンポを上げていきます。
長い拍でダブルタンギングを続けるのは難しいので、最初は短い拍から練習するようにしてみてください。
ポイントは息を止めずにしっかりと流すことです。
タンギングの練習成果をより上位モデルの楽器で試してみませんか?

正しいタンギングを身につけても、やはりグレードの高い楽器で演奏した方が良い音は出しやすいもの。
楽器のグレードを上げて、より充実した音楽ライフを送ってみませんか?
新品の楽器は手が出ない、という方であっても、「服部管楽器」であれば中古楽器も多数取り揃えています!
クラリネットを専門にしているスタッフが、あなたの楽器選びを1から丁寧にサポートします。
下のボタンから、ぜひお気軽にお問合せくださいね♪