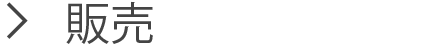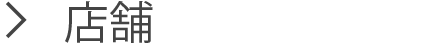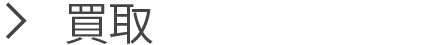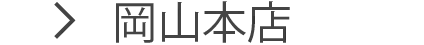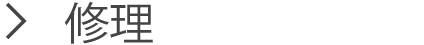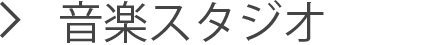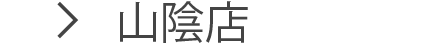サックスを練習している中で、「サックスの高音が思うように出せない」「高音を吹くのは難しい」などと思うことはありませんか?サックスで綺麗な高音を出すためには、いくつかのポイントをおさえておく必要があります。
そこで本記事では、サックスの高音を出したい人のために、サックスで高音が出ない要因や高音が安定する練習方法などを解説します。
- サックスで高音が出ないよくある要因
- 高音を出すために必要な要素
- 高音が安定する練習方法
- サックス高音域のお悩み解決
この記事を読めば、サックスの高音域に関する悩みが解消します。ぜひ最後までお読みください。
サックスで高音が出ないよくある要因

サックスで高音が出ない要因は、主に3つあります。
1つ目の要因は、「息のスピードと圧力が足りない」ためです。サックスの高音は、リードを細かく振動させる必要があります。そのためには、息のスピードが速くなければいけません。息のスピードが足りず圧力が分散すると、音が低くなってしまうため、注意が必要です。
2つ目の要因は、「息を入れすぎている」ためです。上手く演奏ができないと「息をもっと入れなきゃ」と考えてしまう人が多いですが、高音域を出すのに息の量は実はそれほど必要ではありません。
3つ目の要因は、「アンブシュア(口の形)が崩れている」ためです。正しいアンブシュアを保てていない場合、息のコントロールができず、高音を出せません。そのため、アンブシュアを安定させることが重要です。
高音を出すために必要な要素~息のコントロールとアンブシュア
サックスを演奏する際に重要なことのひとつが、息のコントロールです。高音を出すためには速い振動が必要のため、速い息が必須です。
しかし、息を入れすぎると音が裏返ってしまいます。
そのため、息を速くするのに加えて、できるだけ細く息を入れるようにコントロールしなければいけません。
細く・速い息を出すためには、アンブシュアの作り方が非常に重要になってきます。
ポイントは「口の中の容積を狭くする」ことです。
試しに楽器を置いて、口の中の状態を「O(オ)」と発音したような、舌を下げた状態で息を吐いてみてください。
どうでしょうか?細い息も速い息も出にくいのではないでしょうか?
そのため、楽器を吹くときは、口を閉じて何もしていない状態、つまり舌と上顎(あご)が近い、口の中が狭い状態で演奏することが必要になってきます。
発音としては、口の中は「I(イ)」の状態に近いです。
こうすれば細く・速い息を出すことができるようになります。
ただし、口の中を「イ」の形にしても、マウスピースを噛まないようにするよう、注意が必要です。
そのため、口の中は「イ」と狭い状態にしていても、口先だけは「U(ウ)」という、マウスピースを唇の周りの筋肉で包み込むような形にすることが必要です。
マウスピースを噛んでしまうと、リードの振動が妨げられてしまいます。
サックスの音は、リードの振動によって生まれますので、ロスが大きくなってしまうということです。
アンブシュアの全体的な解説はこちらの記事で解説しています。アンブシュアに悩んでいる方にとっては有益な記事となっていますので、ぜひお読みください。
>【初心者向け】サックスのアンブシュアの作り方・吹奏楽奏者必見!
初心者でもできる!高音が安定する練習方法

サックスの高音を安定させるためにおすすめの練習方法を紹介します。
ロングトーン
1つ目は、「ロングトーン」を使った練習方法です。ロングトーンは、名前の通り音を伸ばす練習のことです。
ロングトーンは、音をまっすぐ伸ばすという単純な練習であるため、奏法を確認しやすいというメリットがあります。
曲になってしまうと、指回しやリズムなどに気を取られてしまい、正しい高音域の奏法にするための脳の容量が足りない可能性が高いです。
- 口の中は狭くできているか
- 細く・速い息を出せているか
- 息は入れすぎていないか
このあたりのポイントを確認しながら、ロングトーンをするようにしましょう。
慣れてくると無意識のうちに高音域を吹く際に、適した奏法になってきます。
無意識とは、何も考えずにその奏法が自然にできることを指します。
サックスを始めて数ヶ月もすれば、「下唇を巻く」と意識しなくても、自然に下唇を巻いて構えるでしょう。
これと同じように、ロングトーンを続けていくと、無意識のうちに正しい高音域の奏法ができるようになってきます。
音階・スケール練習
2つ目は、「音階・スケール」練習です。
ただ音階をやるだけではなく、サックスが使える全音域を使って音階・スケール練習をすることで、高音域を使うことに慣れていきます。
普通の曲を吹いていると、高音域に触れる機会は少なくなってしまいます。
そこで全音域の音階を日ごろから行うことで、高音域を使うことに抵抗を無くすことが大切なのです。
おすすめの音階の教本はこちらの「Perfect Scale for Saxophone vol.1 Basic」です。
サックスを吹き続ける限り、一生使える教本ですので、ぜひ手に取ってみてください。
音階・スケール練習は高音域を身につける以外にもメリットがたくさんあります。
音階・スケール練習に関してはこちらの記事で解説しています。サックスの上達に必要な情報となっていますので、ぜひ読んでみてください。
>サックスのスケール・音階練習、正しい練習方法とメリットについて
ピッチ確認しながら練習することも重要
高音域の練習では、ピッチ確認も重要です。チューナーやチューナーアプリを活用して、音程を合わせながら練習しましょう。
音程が悪いと、他の奏者と音が合わなかったり、伴奏と音がズレたように聞こえたり、音痴に聞こえたりします。そのため、練習に慣れてきたらチューナーを使い、音を安定して出せているかを確認してください。
特に高音域の音程が低い場合は要注意です。高音域の音程が下がってしまうと音痴に聴こえやすくなってしまいます。
多少音程が高い場合は、そのままで大丈夫なケースが多いので、奏法や音色などに注意を払いましょう。
サックス高音域のお悩み解決~出ない・裏返る・音が汚い・音程悪い
ここではサックスの高音域を吹くにあたって、よくある悩みを解決したいと思います。
高音が出ない
高音が出ない方は、息のスピードが足りない、というケースが多いです。
口の中が狭くできているか、舌が下がっていないかを確認してみましょう。
ただし、スピードを上げたいがために、マウスピースを噛んでしまうのはNGです。
また、腹式呼吸で深く息を吸う(横隔膜がしっかり下がったことを確認する)と、息のスピードを上げやすいので試してみてください。
高音が裏返る
高音が裏返る方は、息を入れすぎているケースが多いです。
ムキになって息を入れるのではなく、少し楽に演奏するように心がけましょう。
高音の音が汚い
高音に限らず、音色が汚いという方は、息が太くなってしまっているケースが多いです。
息が太いと、本来当たらなくてもよいツボに息が当たってしまうため、雑音的な汚い音が乗ってしまいやすくなります。
サックスの良い音が鳴るツボは本当に小さいです。この小さいツボからはみ出ないように、細く息を当てる必要があるのです。
高音の音程が悪い
音程が低くなりすぎてしまう方は、口の中が狭くできていない、舌が下がっているケースが多いです。
また、音程が高くなりすぎてしまう方は、マウスピースを噛み過ぎているケースが多いです。
ただし、前述した通り、高音域の音程は少し高くなってしまっても問題はありません。
【番外編】フラジオについて
サックスの通常の運指では出せない、音域外の高音を出す方法を「フラジオ」と言います。
フラジオには独特の運指と、フラジオならではの奏法があります。
フラジオに関しては、こちらの記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
>【サックスのフラジオ】運指表と当てるためのコツ(アルト・テナー編)
上級モデルの楽器に持ち替えて、高音域のストレスを無くしてみませんか?

高音域は正しい奏法で出すことができますが、やはりグレードの高い上級モデルの方が高音を出しやすいというのも事実です。
今の楽器を下取りに出して、よりグレードの高い楽器を購入してみませんか?
「服部管楽器」では、サックスの高価買取を実施しているうえに、中古楽器も豊富に取り揃えているので、安価で楽器のランクアップを行うことができる環境となっています。
「服部管楽器」ではサックスを専門にしているスタッフが、あなたの楽器選びを1から丁寧にサポートします。
見積だけでも可能ですので、下のボタンから、ぜひお気軽にお問合せくださいね♪