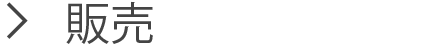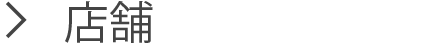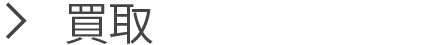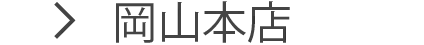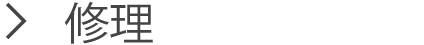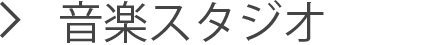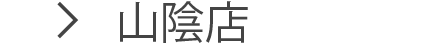「ラクールの練習曲をやるよう言われたけど、どのようなことに意識して練習すればいいか分からない」このような悩みはありませんか?
実はやみくもにラクールを演奏していても、上達スピードは上がってきません。
そこでこの記事では、サックス歴20年、サックス講師も行っている著者が、効果的なラクールの使い方をお教えします。
著者自身、ラクールは全ての曲を勉強しましたし、レッスンでラクールの指導も行っています。
この記事を読めば、より効果的なラクールの練習方法を身につけることができるでしょう。
ぜひ最後までお読みください。
ラクールとは
前提としてこれから解説していく、ラクールとは何か、という解説を一応しておきたいと思います。
ここで言うラクールとは、サックス奏者のラクール氏が書いた「50の易しく斬新的な練習曲」のことです。
1・2巻に分かれて発行されており、各巻に25曲ずつ、合計50曲が掲載されています。
ラクールはサックス吹きにとって避けては通れない、バイブル的なエチュード・教本です。
著者が会ったサックスが上手な方で、ラクールを学んでこなかった方はまずいません。
演奏を聴けば、その方がラクールを学んできたか、学んでこなかった又は惰性でしか取り組まなかったかはすぐに分かります。
それほどラクールは重要なエチュードである、ということをご理解いただけたでしょうか。
ラクールの学び方
ここからはラクールの効果的な練習方法、学び方を解説していきます。
徹底的に譜面通りにこだわる
まずは「徹底的に」譜面通りにこだわるようにしましょう。
ラクール、特に前半の番号は音数も多くなく、それほど難しい曲、というわけではありません。
サックスを吹いて数ヶ月もすれば吹けてしまう、という方も多いのではないでしょうか?
ですがそれはただ譜面をなぞっただけの演奏になりがちです。
本当に楽譜通りに吹けているのか、よく自分の音を聴いてみましょう。
譜面通りになりにくいのはダイナミクスです。
fとpの差、きっちりついているように「聴こえて」いますか?
吹き方を変えているから、fとpの差がついているように演奏者はとらえがちです。
しかし、客観的によく自分の音を聴いて、本当に差がついているかを確認してみてください。
「自分がどう演奏しているか」よりも、「周りにどう聴こえているか」の方がはるかに重要です。
fとpの差がついてるように聴こえない場合、息のスピードが一定であることが問題かと思います。
fは「大きく」、pは「小さく」と音楽の授業で習いますので、どうしても意識が音量にいってしまうことは無理からぬことでしょう。
しかし、音量だけを変えても(何デシベルという世界)fとpの差はわかりにくいままです。
fとpの差は鮮明に表すには、「音色を変えること」が重要になってきます。
具体的には、fは息のスピードを上げて、硬めのはっきりとした音色で作りましょう。
反対に、pは息のスピードを遅くして、柔らかい音色を使用します。
息のスピードを意識して、曲を作ってみてください。
レガート奏法を身につける
ラクールの前半の番号で身につけるべき奏法として、重要なのが「レガート奏法」です。
サックスのレガート奏法は、「ロングトーンのようにまっすぐ伸ばし、指だけ動かす」というのが正しい奏法になります。
ロングトーンと同様なので、息の入る量や方向、アンブシュアなどは変えずに一定で演奏するのが原則です。
サックス吹きで多くの方は、音1つ1つで歌ってしまい、レガートにならないことをよく見かけます。
また、ロングトーンのように伸ばす、というのは一見簡単そうに思えますが、音域によって抵抗感が変わるため、意外と難しいです。
レガート奏法ができるかできないかによって、演奏は劇的に変わりますので、しっかりと身につけるようにしましょう。
1曲を通しで練習してみる
1曲を止まらずに、最初から最後まで通して演奏してみましょう。
間違えてしまっても、途中で止まらず、最後まで演奏しきることが重要です。
ソロ曲の演奏経験のない吹奏楽部などで活動してきた方は、特に苦しく感じるのではないでしょうか?
吹奏楽の合奏だけやっていると、1回メロディを吹いたら、数小節休みがあったり、息が苦しいときはカンニングブレスも使えます。
このようにスタミナをつける練習としても、ラクールは効果的です。
後半になるとだんだん息が吸えなくなり、息が足りなくなってくる感覚になってくる方はスタミナ不足です。
実は息が吸えなくて、足りない感覚を感じる場合、本当に息が足りていない可能性もありますが、息が余っているケースも多くあります。
息が足りないのか、余っているのかを判断するには、演奏をし終えて脱力したとき、息を吐いたか吸ったかで判断できます。
息を吸ったら息が足りていなかった、息を吐いたら息が余っていた、ということになります。
息余りは、息を吐き切らずに演奏を続けていると、長い時間にわたって古い息が残ってしまい、苦しくなってしまう、という現象です。
息余りの対策としては、1フレーズ吹き切るのに必要なだけ息を吸うことと、余分な息をマウスピースの外から吐き出してしまう、という方法があります。
メトロノームを使う練習と使わない練習を併用する
曲の練習し始めは、メトロノームを使って欲しいですが、慣れてきたら1度メトロノームなしで演奏してみましょう。
そこで演奏を録音して、演奏を聴きながら手拍子をしてみます。
この手拍子、一定のリズムで叩けましたか?一定のリズムで叩けないとしたら、それはテンポが安定していないからです。
メトロノームがなくても、テンポを維持できるスキルを「テンポキープ」と言います。
吹奏楽で指揮者のテンポにだけ合わせて練習していると、なかなかテンポキープの力は身につきません。
テンポキープは意外と難しいテクニックではありますが、ソロやアンサンブルを演奏するのに必須となるスキルです。
ラクールを通じて、身につけておきましょう。
スタッカートを鍛える
ラクールも8番、10番あたりからスタッカートが登場してきます。
特に10番・21番・24番ほどスタッカートが登場するのは、通常の曲では考えにくいです。
スタッカートはサックスは苦手な奏法でもあるので、ラクールで克服しておきましょう。
具体的な練習手順としては、まずは前述したレガートで、タンギングなしで演奏できるようにします。
次にスタッカートではなく、普通のタンギングで演奏してみます。
最後にスタッカートを入れて、楽譜通りに演奏する、といった手順で行いましょう。
スタッカートのポイントは、「普通のタンギングで舌がリードにつく時間が長いだけ」で演奏できるようにすることです。
スタッカートだからと言って、息の入れ方やアンブシュアをレガートから変えてしまったり、舌を通常のタンギングよりも強くついてしまったりすることはありません。
正しくスタッカートができるように、練習してみてください。
他のエチュードと組み合わせて練習しよう
ラクールは素晴らしいエチュードではありますが、万能ではありません。
テクニックなどを磨くには不十分です。
ラクール以外のおすすめエチュードについては、こちらの記事にまとめていますので、ぜひお読みになってください。
練習の成果をより上級モデルの楽器で披露してみませんか?

ラクールを使って上達した演奏を、よりグレードの高い楽器で披露してみませんか?
そのために今ある楽器を下取りに出して、新しい楽器を手に入れてみませんか?
「服部管楽器」では、サックスの高価買取を実施しているうえに、中古楽器も豊富に取り揃えているので、安価で楽器のランクアップを行うことができる環境となっています。
「服部管楽器」ではサックスを専門にしているスタッフが、あなたの楽器選びを1から丁寧にサポートします。
見積だけでも可能ですので、下のボタンから、ぜひお気軽にお問合せくださいね♪