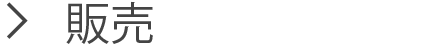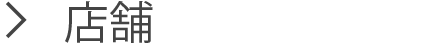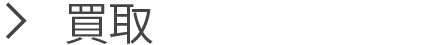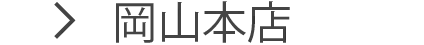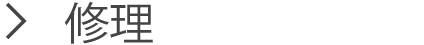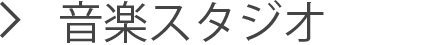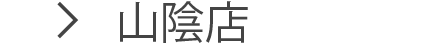「サックスの低音域が上手く出せない」「低音域が裏返ってしまう」こんな悩みはありませんか?
実はこれには明確な奏法の誤りが存在します。
そこでこの記事では、サックス歴20年以上で講師も務める著者が、サックスの低音域の出し方・コツについて余すことなく解説していきます。
この記事を読めば、あなたのサックスの低音域の悩みがきっと解消するはずです。
ぜひ最後までお読みください。
まずは楽器の調整を疑う
低音域が出ない際にまずやってほしいことは、楽器の状態を確認することです。
キーを押すと、肉眼ではしっかりと穴をふさいでいるように見えますが、定期的な調整・メンテナンスをおろそかにすると、実は息が漏れていた、ということがあり得ます。
リペアマンにサックスの調整を依頼すると、楽器本体の中に電灯を入れて、キーをふさいだとき光が漏れていないかをチェックするのを見かけたことがある方も多いでしょう。
あれはキーからの息漏れがないかをチェックしているのです。
キーから息が漏れている状態では、これから解説していく低音域の奏法をどれだけ意識しても、サックスの低音を出すのは難しくなります。
リペアマンに定期調整をお願いするのは、半年に1回程度が理想です。
半年以上、調整に出していない場合は、1度リペアマンに楽器を診てもらうことをおすすめします。
また、自分でもサックスのキーのふさがりを確認できる簡易なチェック方法があります。
その方法は、下のドの音をロングトーンしながら、G#キー(ソ#のキー)を押したり離したりするだけです。
G#キーを押したときに、ビブラートをかけたように音程が上下する場合は、キーのふさがりが甘いことが確定します。
ウルフトーン
低音域の音が常時震えるようなノイズが入ってしまう場合、「ウルフトーン」と呼ばれる現象になっている可能性があります。
ウルフトーンは楽器本体に問題がある場合があるので、奏者側からはどうすることもできません。リペアマンの領域になります。
ウルフトーンが発生する原因は諸説あると言われていますが、次の2つが有力な説のようです。
①楽器の調整不良
②楽器自体の共鳴に問題のあるもの
ウルフトーンが疑われる場合、まずは上級者に自分の楽器を吹いてもらってみてください。
上級者が演奏して、同じ事象が発生しないのであれば、演奏者側の奏法の問題なので、ロングトーンを徹底するなどして、音が震えるのを直しましょう。
上級者が吹いても同じように音が震える場合、いよいよウルフトーンが疑われます。
ウルフトーンが発生している場合、信頼のおけるリペアマンに相談してみましょう。
低音域の奏法
サックスの低音域が出しやすくなる奏法はいくつかありますので、順に解説していきます。
マウスピースを噛まない
まずはマウスピースを噛み過ぎない、ということが非常に重要になってきます。
試しにマウスピースを少しだけ噛んで、低音域を演奏してみてください。
少し噛んだだけで、狙った音のオクターブ上の音に簡単に行ってしまうことが分かります。
楽器を吹こうとするとき、音の立ち上がりのときにこのオクターブ上の音が混じってしまい、裏返ってしまう方をよく見かけます。
中音域・高音域から低音域にレガートで下がる場合にひっくり返る方も同様です。
少し噛んだだけでもオクターブ上の音に裏返ってしまうので、相当噛まないように意識づけをしないと上手く低音域は立ち上がることができません。
サックスを演奏するにあたっては、マウスピースは噛む必要がないことをよく理解しておいてください。
特に顎(あご)の力を使ってしまうと良くありません。唇の周りの筋肉で締める意識でアンブシュアを作ってみましょう。
アンブシュアに関しては、こちらの記事でも詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。
>【初心者向け】サックスのアンブシュアの作り方・吹奏楽奏者必見!
息のスピードを落とす
低音域は息をたくさん入れるのは大前提ですが、息のスピードを落とすということも重要になってきます。
前述したマウスピースを噛んだ時と同様、息のスピードを上げて低音域を演奏すると、簡単にオクターブ上の音になってしまいます。
息のスピードは音の立ち上がり時に速くなりすぎないように注意しましょう。
低音の立ち上がりが裏返ってしまうのは、マウスピースの噛み過ぎか、息のスピードが速すぎるかのどちらか(もしくは両方)の可能性が高いです。
息を下向きに入れる
息を下向きに入れると、低音域が出しやすくなることがあります。
息の向きを変えるのに重要になってくるのは、下顎の位置です。
下顎をより引くと、下方向への息が出しやすくなります。
息の方向をどの程度変化させるかは、使用している楽器やセッティングによって異なるので、よく研究してみてください。
セッティングを見直してみる
低音域を見直すには、セッティングを見直すことも重要になってきます。
マウスピース・リードを軽いものに変更する
マウスピースの開きを狭いモデルに変えたり、リードの番手を下げると低音域は出しやすくなる傾向があります。
どうしても太い音色や響きの豊かさを重視したいがために、重たいセッティングを選択する方も多くいらっしゃいますが、それではコントロールがままなりません。
重たいセッティングにするほど、抵抗感が強くなることで、より息の量が必要となり、低音域を出すのが難しくなります。
ちなみに著者自身も重たいセッティングは好みません。音を狙ったところで出す、というコントロールを重要視しているからです。
1度楽に低音域が出るセッティングに変えてみてはいかがでしょうか。吹奏感が大きく変わります。
マウスピース・リードをきちんと選定する
同じ型番のマウスピースやリードであっても、個体差はかなり大きいものがあります。
いわゆるハズレのマウスピースやリードを選択してしまうと、低音域はおろか、どの音域であっても上手く出ることはありません。
ある意味、技術を磨くのと同じくらいマウスピースやリードの選定は重要です。
サックスは口に近いパーツほど、演奏に与える影響が大きいため、マウスピース・リード選びは、楽器本体よりも重要になってきます。
良いマウスピースやリードを選ぶためには、矛盾しているようですが、「良い音を出そうとしない」ことが重要です。
つまり、いつもの自分の奏法を変えて、道具に合わせてしまっては良くないということです。
自分の奏法を貫いて、良い音がしたものを選ぶ。自分の奏法を変えなければよい音がしないものは選ばない、このくらいの割り切りは必要となります。
とはいえ選定にはある程度技術が必要になりますので、自信がない方はプロの選定品を購入するようにしましょう。
口の形や奏法に違いがあるため、本当は自分で選ぶのが理想ですが、プロの選定品でも80~90点は取れます。
なお、リードは育て方によっても状態が大きく変化します。リードの育て方についてはこちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
コントロールのしやすいより上質な楽器に持ち替えてみませんか?

グレードの高い楽器は、低音域に限らずコントロールがしやすいです。
今ある楽器を下取りに出して、新しい楽器を手に入れてみませんか?
「服部管楽器」では、サックスの高価買取を実施しているうえに、中古楽器も豊富に取り揃えているので、安価で楽器のランクアップを行うことができる環境となっています。
「服部管楽器」ではサックスを専門にしているスタッフが、あなたの楽器選びを1から丁寧にサポートします。
見積だけでも可能ですので、下のボタンから、ぜひお気軽にお問合せくださいね♪