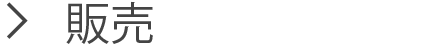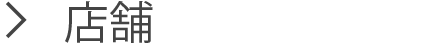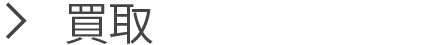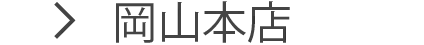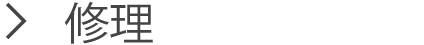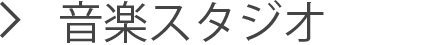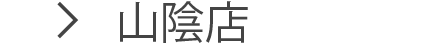「サックスを吹いていると、ズルズルと唾の音のようなノイズが入ってしまう」このような悩みはありませんか?
ノイズが入るのには明確な理由があるため、取り除くことは可能です。
そこでこの記事ではサックス歴20年以上、講師も行っている著者が、サックスのノイズの取り除き方について解説していきます。
この記事を読めば、あなたの悩みの種であるノイズからおさらばすることが可能です。
ぜひ最後までお読みください。
取り除くべき悪いノイズ
それでは取り除くべき悪いノイズの種類と、そのノイズの解消方法を解説していきます。
ウォーターノイズ
ウォーターノイズとは、冷えた管に息を入れることで、暖かい空気が管の中に入り、管の中に結露が発生してしまうことで発生します。
管の中の結露によって、水が溜まってしまうと、演奏する際に「ズルズル」といったノイズが入ってしまいます。
管体が冷えやすい冬場や、エアコンが強く効いている夏場などにウォーターノイズが発生することが多いです。
サックスの構造上、水が溜まりやすいのはオクターブキーとなります。
まずはどの音でズルズルといったウォーターノイズが入っているか確認してみましょう。
ウォーターノイズが真ん中のレ~高いソ#までで発生すれば第1オクターブキーに、高いラより上の音で発生すれば第2オクターブキーに水が溜まっていることになります。(もちろん、両方のオクターブキーに、同時に水が溜まることもあるのでご注意を。)
第1オクターブキーに水が溜まっていると分かった場合、第1オクターブキーを開いた状態にして、そのキーがふさいでいる穴を目がけて強く息を吹きかけます。
吹きかけた息によって、水が飛んでいくのです。
第1オクターブキーが分からない場合、ソの運指にして、オクターブキーを押したり離したりしてみてください。
その際に動いているキーが第1オクターブキーです。
第2オクターブキーに水が溜まっていると分かった場合、まずネックを本体から外します。
ネックの本体とつなぐ部分の穴をハンカチなどを使って押さえ、第2オクターブキーを持ち上げます。

この状態で、楽器を吹くのと同じ要領で、強く息を吹き込みましょう。
こうすることで、唯一あいている第2オクターブキーの穴から水が飛び出ていきます。
ただし、バリトンサックスやネック一体型のソプラノサックスは第2オクターブキーの位置が違います。
ラの運指にして、オクターブキーを押したり離したりして、第2オクターブキーの位置を探してみましょう。
そして第1オクターブキーと同じ要領で、第2オクターブキーがふさいでいた穴を目がけて強く息を吹きかけます。
リードによるノイズ
音域に関係なく、全音域でズルズルといったノイズが鳴る場合、リードを疑います。
ノイズは先ほど解説したウォーターノイズのように、「ズルズル」といった水を含んだような音が鳴ります。
まずはリードをマウスピースから外し、リードの裏面(マウスピースに接する側)の水分を取ってみましょう。
演奏中でリードを外す時間がない場合、リードに乗った水分を吸い取るつもりでブレスを取ることもあります。
それでもノイズが発生する場合は、時間をおいてリードをしっかり乾かしてみます。
まだノイズが発生する場合は試しに他のリードで演奏して、ノイズが入るかどうかをチェックしてみてください。
他のリードでノイズが鳴らない場合は、ノイズが鳴るリードは既に寿命を迎えている可能性があります。
ノイズはいつか入ってしまうもので、仕方のないことであると言わざるを得ません。
しかし、リードの育て方、新品のリードを開けてからどのように吹いてきたかで、ノイズが入るまでの期間を大きく延長することができます。
リードは湿らせる→乾くというサイクルで徐々に状態が変化していきます。
新品で開けたてのリードというのは、この状態変化の度合いが強く出やすいです。
つまり新品のリードを長時間吹く(=水分を多く含ませる)と、短期間しかもたないリードになってしまいがちです。
新品のリードは1分だけ吹く。そこから数分→十数分→数十分と少しずつ演奏時間を伸ばしていく必要があります。
リードは湿らせる→乾くのサイクルを上手く行うことで、劇的に寿命が延びるようになります。
サックスのリードの育て方については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。
ウルフトーン
低音域の音が常時震えるようなノイズが入ってしまう場合、「ウルフトーン」と呼ばれる現象になっている可能性があります。
ウルフトーンは楽器本体に問題がある場合があるので、奏者側からはどうすることもできません。リペアマンの領域になります。
ウルフトーンが発生する原因は諸説あると言われていますが、次の2つが有力な説のようです。
①楽器の調整不良
②楽器自体の共鳴に問題のあるもの
ウルフトーンが疑われる場合、まずは上級者に自分の楽器を吹いてもらってみてください。
上級者が演奏して、同じ事象が発生しないのであれば、演奏者側の奏法の問題なので、ロングトーンを徹底するなどして、音が震えるのを直しましょう。
上級者が吹いても同じように音が震える場合、いよいよウルフトーンが疑われます。
ウルフトーンが発生している場合、信頼のおけるリペアマンに相談してみましょう。
鳴ってしまっていても良いノイズ
ノイズ=「悪」とは言い切れません。
ここからは著者自身が入ってしまっても良いと考えるノイズについて、解説していきます。
低音域を強く演奏したときに鳴るノイズ
例えば低音域をfで演奏したときに鳴る「ビリビリ」といったノイズは、曲の雰囲気によっては使っても良いノイズであると考えています。
あえてこのノイズを乗せることで、他の部分と音色の変化をつけることができるようになります。
このノイズを上手に使っていると感じる楽器はチェロです。チェロの低音域をYouTubeなどで聴いてみてください。
「ビリビリ」とノイズは乗っていますが、不快な感じはしないと思います。
息が管の中を通るノイズ
同じく息が管の中を通るノイズについても、曲の雰囲気によっては使っても良いノイズに分類されると考えています。
通常の音を原色に例えると、息の音が混じった音は絵の具と水を混ぜたような淡い色のようなイメージの音を出すことができます。
柔らかい音色を使いたいときに、著者自身も多く用いているので参考にしてみてください。
ただし、同じ息が管の中を通るノイズであっても、ブレスの際に発生しているノイズは悪いノイズに分類されますので、注意してください。
ブレスは必ず管の外から取るようにしましょう。
よりグレードの高い楽器で上質な音色を手に入れてみませんか?

ノイズを避けることはどの楽器でもできたとしても、音色はやはりグレードの高い楽器の方に軍配が上がります。
今ある楽器を下取りに出して、新しい楽器を手に入れてみませんか?
「服部管楽器」では、サックスの高価買取を実施しているうえに、中古楽器も豊富に取り揃えているので、安価で楽器のランクアップを行うことができる環境となっています。
「服部管楽器」ではサックスを専門にしているスタッフが、あなたの楽器選びを1から丁寧にサポートします。
見積だけでも可能ですので、下のボタンから、ぜひお気軽にお問合せくださいね♪