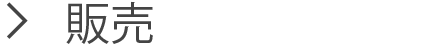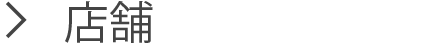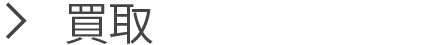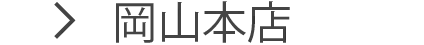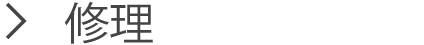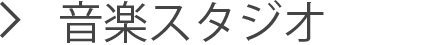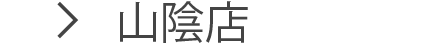吹奏楽やオーケストラで使われるトランペット。輝かしい音色が特徴のトランペットは、初心者でも始めやすい楽器のひとつです。本記事では、トランペットを始めたばかりの方たちのために、初心者が練習する上で重要なポイントや基礎練習、おすすめの課題曲などを解説します。
- トランペットの特徴と種類
- 初心者がトランペットを練習する上で重要なポイント
- 初心者におすすめな基礎練習
- 初心者におすすめの課題曲
最後に、おすすめの音楽教室も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
トランペットの特徴と種類

トランペットの歴史は古く、数千年前までさかのぼります。当時は木や樹皮などで作られており、宗教儀式や軍隊で使われていました。14世紀以降に金属製のトランペットが作られましたが、息の通り道を切り替えるバルブ装置が無かったため、唇のみで音色を奏でていました。その後、18世紀以降にバルブ装置が開発され、現在のようなトランペットの形になったと考えられています。
まずは、トランペットの特徴と種類について、詳しく解説します。
トランペットの特徴
トランペットは、真鍮(しんちゅう)と3つの短い管で作られています。バルブを使って短い管を操作し、音の高さを調整します。ただし、バルブを使うだけではなく、唇を振動させることも必要です。また、チューニングスライドを使うことで、管の長さを微調整できるため、音の高さも細かく調整できます。
トランペットは、金管楽器の代表といえるような存在で、華やかで輝かしい音色が特徴です。メロディを担当することが多く、吹奏楽やオーケストラ、ジャズなどで活躍します。
5つのトランペット
トランペットには、主に5つの種類があります。それぞれの特徴と使われるジャンルについて、詳しく紹介します。
B♭管トランペット
B♭管トランペットは、一般的なトランペットとして知られている種類です。ドの音がピアノの「B♭」にあたることから、B♭管トランペットと言われています。
一般的に、吹奏楽やオーケストラ、ジャズでの花形として活躍します。幅広いジャンルに対応できるため、初心者におすすめのトランペットです。
C管トランペット
C管トランペットは、B♭管トランペットに次いで演奏者が多いと言われています。ドの音がピアノの「C」にあたり、B♭管トランペットよりも高くて明るい音色が特徴です。オーケストラや、クラシックでよく使用されています。
ピッコロ・トランペット
ピッコロ・トランペットは、B♭管トランペットより1オクターブ高い音を出し、輝かしく華やかな響きが特徴です。主にバロック音楽で使用され、さまざまな場面で活躍します。また、近現代音楽やブラス・アンサンブルでも、持ち替え楽器として使われることがあります。
コルネット
コルネットは、B♭管トランペットやC管トランペットよりも、柔らかい音色が特徴です。コンパクトで丸みがあり扱いやすいことから、小学校のブラスバンドで使われます。
フリューゲルホルン
「ホルン」という名前が付いていますが、トランペットの種類のひとつです。B♭管トランペットやC管トランペットよりも縦横ともに一回り大きく、管は「円錐管」になっています。非常に柔らかく暖かい音が特徴で、ジャズで使われる機会が多い楽器です。
初心者がトランペットを練習する上で重要なポイント

トランペットを含む金管楽器は、ここを押せばこの音が鳴ると決まっているわけではありません。息のスピードを利用して、音の高さをコントロールする必要があります。そのため、基礎の練習は非常に重要です。
毎日10分ずつでもいいので、しっかり練習して感覚を掴むことが、上達への近道です。
ここからは、上達のスピードをさらに上げるために、初心者が押さえておくべきポイントを紹介します。今回紹介するポイントは、以下の3つです。
- 重要なのは息の使い方である
- 正しい口の使い方や姿勢を意識する
- 無理矢理高い音を出そうとしない
それぞれ、詳しく解説します。
重要なのは息の使い方である
トランペットは、バルブで音階を調整することが可能ですが、息のスピードで音階をコントロールしなければいけません。低い音を出すためには息のスピードを遅く、高い音を出すためには息のスピードを早くする必要があります。
低い音は「トォー」、中音域は「トゥー」、高い音は「ティー」のようなイメージで、息を吹き込むと良いです。
また、長い時間演奏するためには、腹式呼吸をすることが重要です。口先だけで息を吹き込もうとすると、1曲しっかり吹くことが難しくなります。
腹式呼吸の練習方法は、以下の通りです。
- 姿勢を正して、おへその上に手を置きます。
- 鼻から4秒ほど時間をかけて息を吸い込み、おへそのあたりが膨らんでいることを確認します。
- 口をすぼめて、お腹の力を抜いて8秒ほど時間をかけて、息を吐きましょう。
上記を意識することで腹式呼吸をマスターし、しっかり息を吹き込めるようにしましょう。
正しい口の使い方や姿勢を意識する
音のスピードをコントロールするためには、口の使い方や姿勢も意識する必要があります。トランペットは、唇を振動させることで発音します。唇を振動させるためには、上下の歯の間を開けて唇をぴったり閉じ、少し横に引っ張ることが重要です。できるだけ口の形を崩さないように息を入れ、唇を振動させましょう。
トランペットは、基本的に左手だけで持ち、力を入れないように心がけましょう。力が入ると管の響きを止めてしまうため、せっかく良い音で演奏しても届きづらくなってしまいます。
また、全身リラックスした状態で構えることも重要です。体に力が入ってしまうと、「バテ」に繋がったり、息のコントロールがしにくくなります。
無理矢理高い音を出そうとしない
初心者によくある勘違いのひとつが、高い音を出すときに口を思い切り引っ張り、思い切り息を吹き込むことです。確かに高い音は出ますが、音が安定せずにバテてしまいます。また、正しい口の形が維持できず、不調の原因になります。
そのため、基本的には口の形は変えずに、息のスピードのみで高い音や低い音を出せるように練習することが重要です。一度癖が付いてしまうと、なかなか正しい口の形に戻すことは難しいため、最初のうちから意識するようにしましょう。
トランペットの上達をしたいなら
GIFT MUSIC SCHOOLへ
初心者におすすめな基礎練習

トランペットを少しでも早く上達させるためには、基礎練習が不可欠です。仕事や学校などで忙しくても、毎日10分でも良いので練習しましょう。毎日の基礎練習の中で、息のコントロールの間隔を掴むことが重要です。
ここからは、初心者におすすめの基礎練習を紹介します。今回紹介する練習方法は、以下の3つです。
- ロングトーン
- タンギング
- リップスラー
それぞれ、詳しく解説します。
ロングトーン
ロングトーンは、同じ音を伸ばす練習のことです。金管楽器の王道の練習方法で、初心者が必ず行うべきとされています。音をどのくらい長く伸ばせるかが重要なわけではなく、正しいピッチで練習し、安定して音を鳴らし続けることに意味があります。
ロングトーンは、アプリのチューナーなどを使いながら練習しましょう。音が安定して出せているかどうかを確認しながら、練習することが大切です。しっかりと息を吸って、自然な状態の口の形を意識することを心がけましょう。
タンギング
タンギングは、舌を使って息を止めることで、音の長さを調整する技術です。タンギングも金管楽器では王道の練習方法のひとつで、上達させるためには必須であるとされています。
タンギングの練習では、舌を歯の裏に付ける感覚で行いましょう。強くつくというよりは、つくスピードを意識することが重要です。また、唇で止める癖がついてしまうと、唇の負担が大きくなる可能性があります。そのため、舌を速く動かす練習を行うことがおすすめです。
リップスラー
リップスラーはタンギングを使わずに、同一のポジションで音の高さを変える奏法のことです。トランペットの中でも、非常に難しい奏法とされています。音を切る吹き方であるタンギングとは異なり、リップスラーは音を切らない吹き方をすることが特徴です。
リップスラーは、息を吐き続けながら息のスピードや量をコントロールして、音程を調整します。唇の微調整と音の量で音程を調整するため、それぞれの音を綺麗に出せる口の形で吹くことが重要です。また、それぞれの音の飛び幅も感覚的に掴まなければいけません。そのため、慣れが必要であり、毎日の練習が必須です。
初心者におすすめの課題曲

最後に、初心者におすすめの課題曲を紹介します。
1曲目は、「聖者の行進」です。4分の4拍子でリズムが取りやすく、もっとも高い音が「ソ」であるため、初心者の練習曲としておすすめです。1オクターブの音域を出すことが難しいと感じる方でも、取り組みやすいでしょう。
また、ロングトーンとタンギングする音が程よく混ざっているため、練習にはうってつけです。綺麗に吹くためには、音の頭をしっかりと吹くことがポイントとなります。テンポが速くて難しいと感じた場合は、テンポを落として練習すると良いでしょう。
2曲目は、「きらきら星」です。「聖者の行進」と同様に4分の4拍子でリズムが取りやすく、もっとも高い音は「ラ」であるため、初心者でも演奏しやすい楽曲です。4分音符と2分音符のみで構成されているため、難易度は高くありません。
また、伸ばす音が少ないため、タンギングの練習としておすすめです。テンポも速くないため、できるだけ一つひとつの音を丁寧に吹くことを意識して練習しましょう。
3曲目は、「ハッピーバースデー」です。下の「ド」から高い「ド」までしか使用しないため、初心者でも演奏しやすいとされています。テンポもゆっくりなので、焦らず丁寧に弾ける点も練習にピッタリです。
「聖者の行進」や「きらきら星」とは異なり、リズムは4分の3拍子です。他の2曲と比較すると、リズムが取りづらいと感じるかもしれませんが、少しずつ練習することで演奏できるようになるでしょう。
プロに直接見てもらうことで上達のスピードを上げよう

今回は、トランペットの特徴や種類、初心者におすすめの練習方法、課題曲などを紹介しました。独学でトランペットを練習することも良いですが、音楽教室に通って教えてもらうことも上達への近道です。一人ひとり体格や癖は異なるため、適切な方法で演奏できているかどうかが、自分では気が付きにくいためです。
GIFT MUSIC SCHOOLでは、実際に活躍しているプロの音楽家が1on1でレッスンをします。プロが目の前で見本を見せながら教えてくれるため、何ができていて何ができていないのかが分かります。また、どのように改善していけば良いかを言葉で説明するため、圧倒的に上達スピードが上がるでしょう。
GIFT MUSIC SCHOOLでは、体験レッスンも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
トランペットの上達をしたいなら
GIFT MUSIC SCHOOLへ