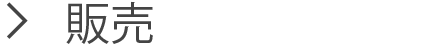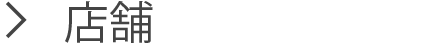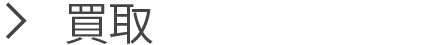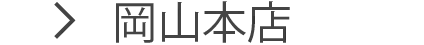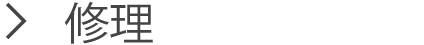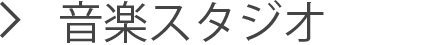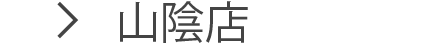「いつかはプロが演奏しているようなスーパーテクニックで演奏したい」このような思いはありませんか?
そこでこの記事では、サックス歴20年以上で講師も務める著者が、サックスの特殊奏法について一覧にして解説していきます。
この記事を読めば、いつかものにしたい特殊奏法を演奏するためのヒントを得ることができるようになります。
ぜひ最後までお読みください。
サックスの特殊奏法の種類一覧
サックスの特殊奏法を1つずつ解説していきます。
フラジオ
フラジオ奏法とは、運指表にある最高音(ファ#、一部のHigh-Gキーのついたソプラノサックスはソ)よりも、さらに高音域の音を出すテクニックです。
サックスには実際に鳴っている音(基音)よりも高い倍音という音が含まれています。
その高い倍音部分を強調すると、通常音域よりかなり高い音が出せるようになるのです。
倍音を出すためには、通常音域とは少し違う奏法をする必要があります。
まずは息の量を少なくすることです。
フラジオは大きな音が鳴っているように聴こえるため、息をたくさん入れようとして演奏する人がいますが、実は息の量はほとんど使いません。
少ない息をフラジオが当たるツボに入れることで、フラジオを鳴らすことができます。
フラジオが当たるツボはものすごく小さいです。その小さいツボに当てるために細くまとまった息を使います。
細くまとまった息を出すのに重要なのは「口の中を狭くする」ことです。
口の中を狭くするには、舌の位置が重要です。舌を上顎に近づけるようにして、アンブシュアを作りましょう。
個人的には「KU(ク)」という発音に近いと感じています。
次に、下顎を少し前に出すことで、息の方向を上向きにします。
第2オクターブキーからリガチャーのネジのあたりにフラジオが当たるツボがあることが多いです。
またフラジオは、通常では使わない運指で演奏します。運指に関してはこちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
>【サックスのフラジオ】運指表と当てるためのコツ(アルト・テナー編)
ダブルタンギング
ダブルタンギングは、通常のタンギング(シングルタンギング)では間に合わない、速いタンギングをするときに必要になるテクニックです。
シングルタンギングの速度を上げることは、非常に難しいです。
ある程度のテンポでシングルタンギングができる、中級者以上の方で、更に速いタンギングが必要になった場合は、積極的にダブルタンギングの練習をしていくべきです。
シングルタンギングが「TuTuTuTu(トゥトゥトゥトゥ)」と発音するのに対して、ダブルタンギングは「TuKuTuKu(トゥクトゥク)」または「DuGuDuGu(ドゥグドゥグ)」と発音してタンギングを行います。
「TuKuTuKu(トゥクトゥク)」の方は明瞭なタンギングになりやすい、「DuGuDuGu(ドゥグドゥグ)」の方は「Du」と「Gu」の発音が一定になりやすいというメリットがそれぞれあります。
「TuKuTuKu(トゥクトゥク)」「DuGuDuGu(ドゥグドゥグ)」どちらのタンギングにするにせよ、「リードが触れる舌の位置が2カ所ある」ことを意識することが非常に重要です。
つまり、「Tu(Du)」と発音しているときと、「Ku(Gu)」と発音しているときでは、リードに触れる舌の位置が違っているということです。
「Tu(Du)」は舌の先(シングルタンギングとほぼ同じ位置)でリードについていて、「Ku(Gu)」は舌の奥でリードについています。
舌をリードにつける→舌の位置を戻すという一連の動きで、舌の先と舌の奥の2回でリードにつくため、速いタンギングが可能になります。
シングルタンギングでは使わない、舌の奥を使う「Ku(Gu)」の発音を上手くできるかが、ダブルタンギングの習得できるかの大きな分かれ道です。
、「Tu(Du)」と「Ku(Gu)」の発音では、使う舌の位置は変わりますが、触れるリードの位置は変わりません。
「Ku(Gu)」の発音は舌の奥で、リードから離れているので、少し深めにくわえるとリードと舌の位置が近くなり、コツがつかみやすくなるかもしれません。
ハーフタンギング
ハーフタンギングとは、リードと舌が触れた状態で音を出す演奏法です。
舌をリードにつけ過ぎてしまうと、リードの振動が全て止まってしまうため、音が鳴りません。
そのため、極めて軽く、舌とリードが触れた状態となり、ミュートしたような音が鳴ります。
ハーフタンギングは楽譜で指示されることはかなりまれですが、演奏で使える局面はあります。
その局面とは「レガートが必要だがスラーがかかっていないフレーズ」と「大きな跳躍があった場合」です。
レガートが必要だがスラーがかかっていないフレーズでは、通常のタンギングで切ってしまうと、どうしても音が切れ過ぎて、滑らかに繋がらなくなってしまいます。
そこでハーフタンギングを使うと、音の切れ目が良い意味で不明瞭になり、繋がりやすくなります。
また大きな跳躍がある場合、特にオクターブキーを押した音から、オクターブキーを押さない音へスラーで移行するのはサックスの苦手分野です。
跳躍後の音の前にハーフタンギングを入れると、スラー感が損なわれずに音を移行することができます。
そしてハーフタンギングを身につけておく最大のメリットが、通常のタンギングがきれいになることです。
なぜなら通常のタンギングは、ハーフタンギングよりほんの少しだけ、舌をリードに触れさせれば十分だからです。
多くの人は舌をリードにつき過ぎてしまい、ノイズが入り、タンギングがきれいになりません。
ハーフタンギングをしながら、リードにほんの少しずつ舌をつける力を強めていきましょう。音が出なくなった瞬間が、適切なタンギングの舌づかいです。
スラップタンギング
「パチン」という物を叩いたような音をタンギングで出すのがスラップタンギングです。スラップ(Slap)とは「叩く」という意味です。
通常のタンギングが舌とリードが点と点で触れるのに対して、スラップタンギングでは面と面で触れるように演奏しましょう。
まず舌をリードに密着させて、リードと舌の間に真空状態(=空間に何もない状態)を作り出します。
真空状態が作れると、舌をリードから離した瞬間に、リードが舌と同じ方向につられて動きます。
リードが元の形に戻ろうとしたとき、マウスピースを叩き(Slap)、音が出る仕組みです。
バリトンサックスのような、リードの大きい楽器であるほど、スラップタンギングはやりやすいので、感覚がつかみやすくなります。
しかし、スラップタンギングは演奏の邪魔になってしまっていることが多いのが現実です。
スラップタンギングを使う場合は、楽譜に明確な指示があります。
つまり、楽譜に指示がない場合はスラップタンギングを原則使ってはいけないのですが、スラップタンギングのような音が入ってしまっている方も多く見受けられます。
これは前述したように、舌とリードが面と面でついてしまっているからです。
必ずリードの先端1点をめがけて、舌をつくようにしましょう。
スラップタンギングにならないようにするには、基本のタンギングの奏法が重要になってきます。基本のタンギング奏法についてはこちらの記事で解説しているので参考にしてみてください。
>【サックスのタンギング練習】吹奏楽初心者でも上達する5つのステップ|舌の位置から発音まで完全解説
フラッター
フラッターとは巻き舌で「ドゥルル…」と発音したような音をサックスで出す奏法です。
うがいのように喉を震わすか、巻き舌をしながら演奏することで、音が細かく切れてフラッターになります。
どちらにせよ強い息を出すことを心がけてください。
巻き舌を使って、フルートは比較的このフラッターを簡単に行うことができますが、サックスの場合は難しくなります。
音程が下がりやすいので、アンブシュアが緩み過ぎないように注意して演奏してください。
ポルタメント
起点の音から終点の音まで、滑らかにつなぐテクニックです。トロンボーンのスライドで滑らかに音程をつなぐのをイメージすると分かりやすいかもしれません。
運指で起点の音から終点の音まで移行するグリスサンドとは別の奏法となります。
サックスのポルタメントは指とアンブシュアの両方を使います。
上行形の場合、指を動かしたらすぐにアンブシュアを緩め、ゆっくりと指を高い方の指に持っていきます。
指はゆっくり動かしますので、音が移行している間はキーは開いているが開き切ってはいない、半開きのような状態が続きます。
そしてキーを開き切ったら元のアンブシュアに戻します。
下行形はこれの逆ですが上行形よりもさらに難しくなります。
循環呼吸
息を吸いながらも音を出す奏法です。
人間の構造上、息を吸うことと吐くことを同時に行うことはできません。
ではどうするかと言うと、まずは演奏しながら、ほっぺを膨らませて、口の中に空気をためておきます。
ほっぺを元に戻しながら、口の中の空気を押し出す感じで楽器に入れて音を出しつつ、鼻から息を吸います。
息を吸い終わったら、通常の息を吐く奏法に戻して完了です。
口の中にある空気だけで楽器を鳴らすのが難しいポイントです。
特殊奏法を身につけるには土台となる基本奏法が重要
特殊奏法は特別な吹き方が必要になることから、通常奏法とは関係ないと考えている方もいますが、実はそうではありません。
特殊奏法には、奏法の柔軟性が必要となってきますが、それは質の高い基本奏法という土台があってこそのものです。
基礎練習を地道に行うことが、誰しもが憧れるスーパーテクニックの土台となっていることは忘れないでください。
焦って特殊奏法の練習ばかり行ってしまうと、奏法を乱すきっかけとなりがちです。
普段行っている練習をおろそかにせず、地道に行っていくことが、結局は上達への最短距離となります。
より上質な楽器で特殊奏法にチャレンジしてみませんか?

ここで紹介してきた特殊奏法は、より上級モデルの楽器の方が演奏しやすいのは事実としてあります。
これを機に、楽器のグレードを上げてみませんか?
「服部管楽器」では、サックスの高価買取を実施しているうえに、中古楽器も豊富に取り揃えているので、安価で楽器のランクアップを行うことができる環境となっています。
「服部管楽器」ではサックスを専門にしているスタッフが、あなたの楽器選びを1から丁寧にサポートします。
見積だけでも可能ですので、下のボタンから、ぜひお気軽にお問合せくださいね♪