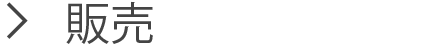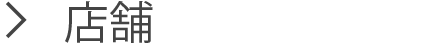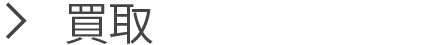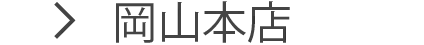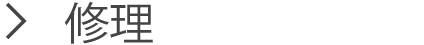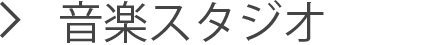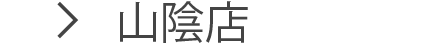「どのような練習メニューを行えば、サックスが上達するのか分からない」こんな悩みはありませんか?
サックスはやみくもに練習してもなかなか上達しません。
実はサックスを上達するための練習メニューは、はっきりと決まっています。
この記事では、30枚以上の吹奏楽CDレコーディング経験のある著者が、サックス上達に効果的な基礎練習について解説します。
この記事を読めば、あなたの上達につながる練習メニューを知り、より充実したサックスライフが送れるようになります。
ぜひ最後までお読みください。
基礎練習で行うべき練習メニュー
全てのサックス奏者が、基礎練習で行うべきメニューは次の通りです。
ロングトーン
ロングトーンとは、1つの音を長く伸ばし続ける練習を指します。
管楽器上達のために必要な、最も基本的な練習のうちの1つです。
一般的には、メトロノームを♩=60程度に設定し、8拍間音を伸ばし、2拍間休むというサイクルを音階などを使って行います。
ロングトーンを行うことで得られる効果は「音が震えずに、真っ直ぐ伸びるようになる」という点です。
初心者の間は、音を真っ直ぐ伸ばすために行う「息を一定量入れ続ける」「アンブシュアを固定する」という技術がありません。
これらの技術を習得したり、演奏をする上での体力を身につけたりすることが、ロングトーンによってできるようになります。
慣れてきたら、最低音や最高音などの出しにくい音のロングトーンや、fやp、クレッシェンドやデクレッシェンドを伴ったロングトーン練習をしてみましょう。
すでに音を真っ直ぐ伸ばすことができる中級者の方にとっても ロングトーンは効果を発揮します。
それはロングトーンには「奏法の見直しと改善ができる」という効果が期待できるからです。
自分の演奏に不満があれば、そのまま演奏していても変わらないので、アンブシュアなどの奏法を見直しますよね?
このように奏法を見直すには、ロングトーンがぴったりです。
なぜなら曲やエチュードでは、指回しやリズムなど、気にしなければならないポイントが多すぎて、奏法まで頭が回りにくいです。
その点、ロングトーンのように音を伸ばすだけのシンプルな練習であれば、奏法の見直しや改善を行いやすいという特徴があります。
著者自身、楽器を始めてから数年は時間があれば、このロングトーン練習を繰り返し行ってきました。
その結果、吹奏楽CDのレコーディングに参加するほどの腕前になれたと自負しています。
それだけ、 ロングトーンは重要な練習、ということができます。
スケール(音階)練習
時間がない場合であっても、サックス奏者にはスケール(音階)練習をするように勧めています。
スケール練習をすることで、「演奏が安定する」「譜読みが速くなる」というメリットを享受することができるからです。
サックスのスケール練習は、次のように行います。
- 調の最初の音で、サックスが出せる1番低い音域からスタート
- その調の音のうち、サックスで出せる1番高い音まで上行する
- その調の音のうち、サックスで出せる1番低い音まで下行する
- 最初に吹いた音まで上行する
このように練習することで、幅広い音域を使うことになり、演奏が安定するようになります。
この形で様々な調が吹けるように練習しましょう。難しいですが長調・短調24調を暗譜で吹けるようになれば、かなり力がついています。
スケール練習では「Perfect Scale for Saxophone Vol.1 Basic」を使うと高い効果を得ることができます。詳細は後述します。
タンギング
音の出だしは、演奏の第一印象を決めるため、非常に重要になってきます。
そのためタンギングの質を上げることは、良い演奏には必要となる要素です。
日々の基礎練習にタンギング練習を取り入れましょう。前述したスケール練習とタンギングを組み合わせるのも効果的です。
サックスのタンギングの練習方法に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。
>【サックスのタンギング練習】吹奏楽初心者でも上達する5つのステップ|舌の位置から発音まで完全解説
ビブラート
サックスのビブラートはかけるだけならそれほど難しくありませんが、きれいなビブラートにするためには相当な練習が必要です。
日頃からビブラートの練習をしておくことで、実際の曲でもビブラートが使えるようになります。
少しの時間でも良いので、日々の練習にビブラートを取り入れてみましょう。
サックスのビブラートの練習方法に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。
>【初心者必見!】サックスのビブラートのかけ方のコツとQ&A集
録音
日々の練習を録音しながら行うことは、上達への近道です。
演奏をしながらだと、自分の音を客観的に聴くことは難しいと思います。そこで役に立つのが録音です。
どのように演奏しているかよりも、どのように聴こえているのかの方がずっと重要です。
自分で演奏している音を聴き、自分の演奏の傾向を知って改善していくことで練習効率は上がります。
特にリズムやテンポ感の乱れはすぐに感じることができるはずです。
録音機材は高価なものを揃えるに越したことはないですが、スマートフォンの録音用アプリでも十分利用できます。
良い音楽を聴く
実際に演奏するだけではなく、良い音楽を聴くことも1つの重要な練習です。
良い音楽を聴くことで、演奏に必要な「イメージ力」を磨くことができます。
どれだけ技術を磨いても、イメージできない音は出すことができません。そのためイメージ力を鍛えるのも立派な練習の1つです。
著者も昔から、移動中や作業中などは良い音楽を聴くようにしていました。
英語にたくさん触れれば、英語の発音が良くなるのと同じで、良い音楽にもたくさん触れれば、必ず良い演奏につながってきます。
ただし注意したいのは、必ず「良い音楽」であることが重要です。
昨今ではYouTubeに誰でも演奏を投稿できるようになったことから、良い音楽に巡り合うことが難しくなったと思います。
またサックス以外の音楽に触れることも、イメージ力の向上には重要です。
オーケストラやピアノ、室内楽など様々な音楽を積極的に聴くようにしてみてください。
基礎練習に準備しておくと良い本・楽譜
基礎練習と合わせて、エチュード(教則本)を併用するのも効果的です。
ここでは初心者におすすめのエチュードを3冊、紹介します。
サクソフォーン教本(大室 勇一)
サックスを始めてすぐ、最初の1冊として取り入れると良いエチュードです。
サックスの音の出すところから、徐々に難しい課題に取り組むよう設計されています。
練習用の楽譜だけではなく、大室先生からのアドバイスも分かりやすく記載されています。
楽器の手入れ方法や音楽の基礎知識についても学ぶことができるので、初学者にはまずおすすめしたいエチュードとなっています。
Perfect Scale for Saxophone Vol.1 Basic(松下 洋)
スケール練習用のエチュードです。
サックスのスケール用エチュードは数多く出版されていますが、このエチュードをおすすめとして紹介する理由は「正しい指番号が明記されている」という点です。他のスケール用エチュードには指番号の記載はありません。
指番号を間違えて覚えてしまうと、将来的に難しい曲にチャレンジしようとした際、必ず壁にぶつかってしまいます。
今までは正しい指番号はレッスンで逐一習うしかありませんでしたが、このエチュードのおかげで独学でも学ぶことができます。
もちろん初心者も使うことのできるエチュードですが、上級者まで幅広く使用できるエチュードです。
末永く使えるので、サックス奏者は必ず手に入れておきたい1冊となっています。
サクソフォーンのための50の易しく漸新的な練習曲(ラクール)
サックス奏者の「音色」と「表現力」を学ぶためのエチュードとなっています。
最初は平易な曲から書かれていますが、徐々に難易度が上がっていきます。
このラクールのエチュードをきちんと学べば、余程難しい曲ではない限り、どんな曲でも演奏することができるようになるでしょう。
ただし、ラクールのエチュードは、曲だけ書かれていてアドバイスが書かれていないので、独学で学ぶのが難しくなっています。
「服部管楽器」は音楽教室も開講しているので、サックスを本格的に学びたい方は問い合わせてみてくださいね。
グレードの高い楽器に買い替えて、よりサックスライフを充実させよう!

もちろん練習も効果がありますが、自分の演奏の質を上げるには楽器の買い替えも候補に入れたいところ。
お手持ちの楽器をランクアップさせてみませんか?
「服部管楽器」では、サックスの高価買取を実施しているうえに、中古楽器も豊富に取り揃えているので、安価で楽器のランクアップを行うことができる環境となっています。
「服部管楽器」ではサックスを専門にしているスタッフが、あなたの楽器選びを1から丁寧にサポートします。
見積だけでも可能ですので、下のボタンから、ぜひお気軽にお問合せくださいね♪